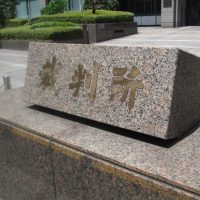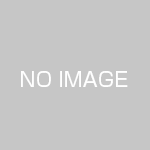このページでは、労働審判の制度がどのようなものかを大まかに理解するため、労働審判制度の概要を弁護士が解説します。
労働審判制度の趣旨
労働審判制度は、近時の個別的労働紛争の増加傾向を背景として、労使間の個別労働紛争を、紛争の実情に即して、迅速、適正かつ実効的な解決することを目的として創設された制度です。労働審判制度については、労働審判法という法律がその手続きの内容を定めていますが、この手続は全て上記の制度趣旨に沿って運用されることになります。
労働審判法 第1条
この法律は、労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争(以下「個別労働関係民事紛争」という。)に関し、裁判所において、裁判官及び労働関係に関する専門的な知識経験を有する者で組織する委員会が、当事者の申立てにより、事件を審理し、調停の成立による解決の見込みがある場合にはこれを試み、その解決に至らない場合には、労働審判(個別労働関係民事紛争について当事者間の権利関係を踏まえつつ事案の実情に即した解決をするために必要な審判をいう。以下同じ。)を行う手続(以下「労働審判手続」という。)を設けることにより、紛争の実情に即した迅速、適正かつ実効的な解決を図ることを目的とする。
労働審判の対象となる事件
個別労働関係の民事紛争
労働審判制度の対象となる事件は、「個別労働関係の民事紛争」に限定されています。つまり、労働審判は「労働関係の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争」を対象としています。 そのため、集団的な労使の紛争(労働組合が当事者となる事件)や公務員の任用関係に関する紛争、労働者間の紛争等は労働審判の対象とはなりません。労働審判の対象となる事件の代表的な類型としては、次のようなものがあります。
- 解雇や配置転換などの効力を争う事案
- 残業代請求などの賃金の支払を求める事案
- セクハラ・パワハラなどに関連して金銭の支払いを求める事案
労働審判に馴染まない事件
労働審判法では、労働審判委員会が、事案の性質に照らし、労働審判手続を行うことが紛争の迅速かつ適正な解決のために適当でないと認められるときは、労働審判事件を終了させることができると定めており、この場合通常訴訟へ移行することになります。こうした仕組みは、労働審判が3回以内の期日で審理を終結するため、事実関係が複雑であったり、法的な判断を下すのに考慮すべき事情が多岐にわたるような事案は、労働審判に馴染まないという考えから定められているものです。 例えば、賃金差別に関する事件、整理解雇に関する事件、就業規則の不利益変更に関する事件、過労死による損害賠償請求事件等がこれにあたると考えられています(もっとも、これらの事件であっても、事案によっては、労働審判に馴染むものもあります。)。
労働審判の当事者・代理人
労働審判の当事者
労働審判では、労働審判を起こした側を申立人、労働審判を起こされた側を相手方と呼びます。申立人は通常の裁判における原告、相手方は通常の裁判における被告にあたります。労働審判では、労働者側からの申立がその大部分を占めていますので、会社や個人事業主といった経営者側は、労働審判の「相手方」という立場で手続当事者となることが一般的です。もっとも、労働審判法は、使用者からの申立は禁じていません。したがって、上記の「個別労働関係の民事紛争」に該当するかぎり、使用者が労働審判の申立人となることも可能です(当事務所においても、申立てをしたことがあります。)。
労働審判の代理人
労働審判法は、労働審判手続きに代理人の選任を強制しているわけではありません。したがって、会社経営者自らが労働審判手続を行うことも法律上は可能です。もっとも、必ずしも会社経営者本人が裁判実務に精通しているわけではありませんので、短期決戦で効率的な主張立証を求められる労働審判においては、手続きについて知識経験を持った代理人を選任することが有効となるケースは多いでしょう。労働審判法では、労働審判における代理人は、原則として弁護士でなくてはならないと定められています(例外的に、弁護士以外の代理人が許可される規定もありますが、実務的には極めて稀です。)。
労働審判手続の主催者・管轄裁判所
労働審判委員会
労働審判手続は、次の3名によって構成される労働審判委員会によって行われます。
- 労働審判官(1名):労働審判の申立てを受けた地方裁判所に所属する裁判官です。
- 労働審判員(2名):労働関係に関する専門的な知識経験を有する者のうち、最高裁判所によって任命された者。具体的な事件の担当は、裁判所が労働者側・使用者側から各1名を指定します。
管轄裁判所
労働審判は、原則として次のいずれかの地方裁判所に申立をすることになります。
- 相手方の住所、居所、営業所若しくは事務所の所在地を管轄する地方裁判所
- 個別労働関係民事紛争が生じた労働者と事業主との間の労働関係に基づいて当該労働者が現に就業し若しくは最後に就業した当該事業主の事業所の所在地を管轄する地方裁判所
- 当事者が合意で定める地方裁判所
労働審判手続きのポイント-通常訴訟との違い
手続きの非公開
労働審判の手続きは、原則として非公開となっています。これは、通常の労働訴訟が公開の法廷で行われることとの大きな違いです。もっとも、労働審判法第16条によれば、労働審判委員会の判断により、相当と認める者の傍聴が許されることがあるとされており、紛争の具体的事情に応じて、会社の人事担当者や労働組合関係者などの傍聴が認められることがあります。
期日の回数制限
労働審判では、原則として審理を行うのは3回に限定されています。期日と期日との間は長くても1ヶ月程度しかとられないため、申し立てから約3ヶ月で全体の手続が終了します。このような限定された回数で審理・判断をすすめる関係上、通常、第1回期日において労働者側と会社側はそれぞれ言い分を全て主張し、証拠も提出します。その後の第2回期日では、調停(和解)ができるかどうかの検討を行い、補充の主張や証拠提出をする必要がある場合にはこれを行います。このような調整の結果、和解ができない場合には、第3回期日において、労働審判委員会から審判というかたちの判断が下されることになります。
労働審判の結果に対する異議がある場合
労働審判委員会が出した労働審判の結果に不服がある場合、当事者は異議を出すことが可能です。この場合、労働審判は失効することになる一方で、事件は地方裁判所における通常の民事訴訟に移行し、労働審判の申立時点で訴えの提起があったものとみなされます(この点、仮執行宣言が付された通常訴訟の判決では、判決に不服があり控訴をした場合であっても、当該判決に基づく強制執行停止の手続きを経ない限り、強制執行が可能となるという部分が異なります。)。